※この記事はInstagramフォロワー様向けに限定公開しています。
※この記事の内容は一般公開ですが、まもなく有料記事にします。
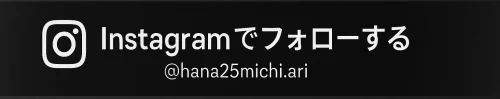
\ 会員限定の特典体験レポを公開中 /
> Instagramでフォローする → [@hana25michi.ari]
HVPCってどんなサロン?|一度退会すると再入会できない“選ばれた空間”
HVPC(Holland Village Private Community)は、Instagramフォロワー19万人超の河村真木子氏が主宰する会員制オンラインサロン。
– 約150の同好会があり、リアルな交流や限定体験が多数
– 入会には審査・紹介制
– 一度退会すると再入会不可
💡HVPSってどんなサロン?
_トレーニング・語学・金融・招待イベントまで_
活動は想像以上にアクティブ!
なんと「毎日なにかがある」オンラインサロン。
📌 例:
– 真木子さんの毎日コラム(コラメ)
– トレーニングクラス(トラメ)
– 英語・韓国語クラス
– 金融・社会学講座・世界情勢
– 会員限定イベント(オフライン&海外も)
🎉 現在は「オンラインサロン」から「オンラインコミュニティ」に進化中!
👉

実は河村真木子さんもこのブログを知っています!
HVPCにはなんと150以上もの同好会が存在します。
いくつかの同好会に参加している私ですが、実は…オフ会は未経験。
本部招待のイベントには喜んで参加していたものの、同好会の集まりはちょっとハードルが高く感じていました。
そんな中、唯一楽しみにしていたのが「能楽同好会」。
黒柳徹子さんのYouTubeでも登場された狂言 三宅一門の奥さまが幹事を務め、
毎回のプチコラムが絶妙に面白く、学びにもなる素敵な同好会です。
そして…なんと新春の手話狂言にご招待いただけることに!
ドキドキのオフ会初参加レポートをお届けします。
📌HVPC人気記事はこちら
- 保護中: 経堂で体験!エンダモロジーで全身ボディケア&小顔効果を実感✨
- 保護中: Holland Village Private Spa で叶う、極上プライベート時間
- また当選!?✨ エンスィ スキンアウェイクニングエッセンスがキター!😇
- 【東京ランチマップ×HVPC】超予約困難!お鮨とシャンパンの楽園「鮨結う遥」体験レポ🍣🥂
- GEODESISの香りと上質特典が話題|HVPCサロン限定プレゼント体験レポ【銀座】
- 保護中: 【当選で初潜入】紹介制「東京アメリカンクラブ」での特別ランチ体験
- 保護中: 【体験レポ】日本一のオンラインサロン「HVPS」がすごすぎた💎 _紹介制サロンのリアルと特典まとめ
- 保護中: 【HVPC特典レポ】南青山の隠れ家サロンで極上フェイシャル&ボディ体験
- 保護中: 【口コミレポ】HVPC特典で体験!プライベートサロン「Odette」の美白フェイシャル✨
📬 お知らせ
今後の限定イベント情報は、Instagramストーリーで告知します📢
[本音レビュー](https://www.instagram.com/hana25michi.ari) をフォローして、最新情報をチェックしてくださいね。
※この記事は一部のフォロワー様向けに限定公開しています。
よかったらSNSも覗いてみてね!
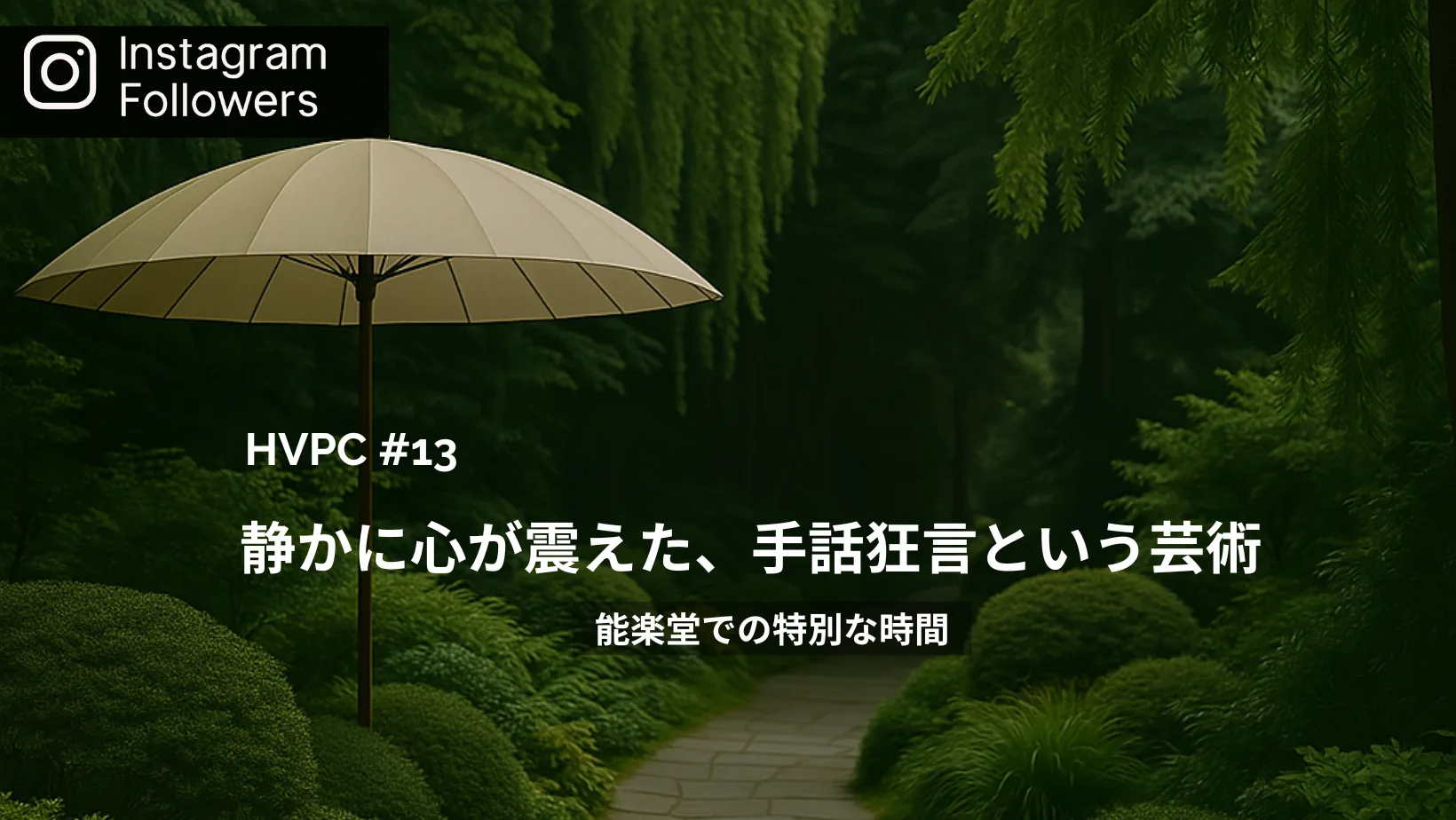


コメント